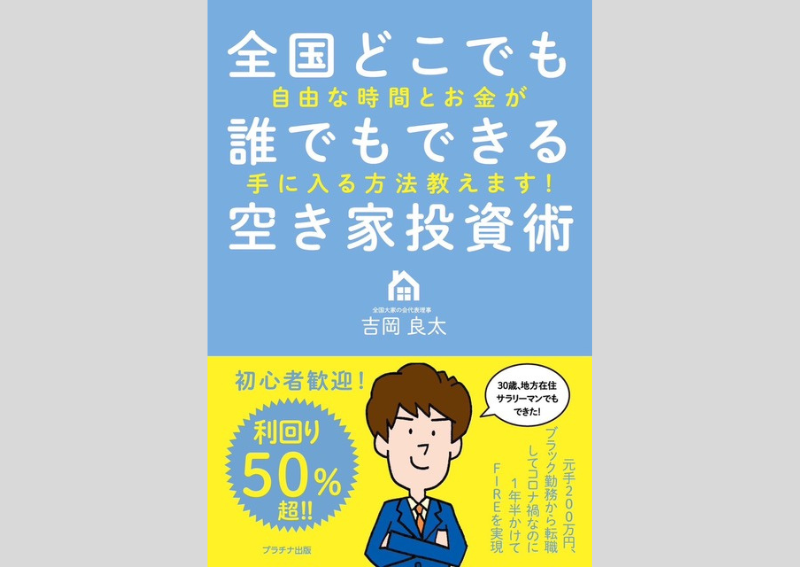大家が主役になる時代の幕開け
2021/04/26

イメージ/©︎Chaiyawat Sripimonwan・123RF
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」がいよいよ全面施行
2020年6月12日に制定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)が、いよいよ21年6月15日に全面施行される(法律のうち、サブリース業者を規制する法律の部分は、既に20年12月15日に施行されている。関連記事はこちらから)。
管理会社を頼まずに家賃の集金から建物の修繕まで全て自分でやっている「自主管理」の大家もいるが、賃貸業全体では少数派だろう。大多数の大家は委託されている内容はさまざまだとしても「管理会社」と取り引きしているはずだ。
この法律が施行されると、一定数以上の管理戸数がある場合、国土交通省に登録をしなければ賃貸住宅の維持保全を含む管理業をすることができなくなる。今回は、この新しい法律が施行される前と後では、大家にとっての賃貸業はまったく違ったものになるということを紹介したい。
この法律がなかった今までは、管理会社が主役だった
どういうことなのか具体例をあげてみよう。大家なら、退去 → リフォーム → 募集 → 契約 → 入居、という賃貸業務のルーティンはお分かりのことだろう。この一つ一つに管理業務の適正性が問われているのだが、次のような経験を持つ大家はいないだろうか?
①入居者から解約通知がでていたのに、管理会社が見過ごしていた
②退去後のリフォーム工事をしなければならないのに、管理会社が発注し忘れていた
③解約通知が出れば「空き予定」でも募集できるのに、管理会社が募集広告を発信していなかった
④申し込みが決まったと思ってリフォーム工事を発注したのに賃貸借契約はキャンセルされた
など、嫌な思いの一つや二つは経験したことがあるのではないだろうか。それでも正直に謝罪して、汚名挽回のために頑張ってくれたなら信頼関係は継続できるものだが、なかには発注を忘れてリフォーム工事が遅れたために入居者を取り逃す事態になったのに「人手不足のために工事業者がみつからなかった」などという、本当のように聞こえる嘘をつかれることもあるのだ。何故このようなことが起こるかといえば、大家と管理会社の間には「情報格差」があるためだ。
次ページ ▶︎ | 大家と管理会社の間には「情報格差」がある
大家と管理会社の間には「情報格差」がある
情報格差とは何か?
それは「管理会社が持っていて大家が持っていない情報」のことだ。さまざまな情報があるが、よく考えてみてほしい。管理会社があなたの物件と同じエリアに、あなたの建物とほぼ同じグレードの建物を管理していないとは考えにくい。そんなとき、客が選ぶ部屋がいつもあなたの物件になるだろうか? ならないこともあるだろう。ライバル物件に客が決めたとき、必ずしも客が主体的に決めたとはいえない事情があったりするものだ。
ライバル物件の大家は、退去後のリフォーム工事代金が明らかに割高と感じても、空き室を早く埋めてくれるのなら文句もいわずに高いリフォーム工事を発注してくれたとしたら? 管理会社の担当者が恩義を感じて、あなたの物件よりもライバル物件を強く勧めたのかも知れない。そんなことはあなたは知る由もない。
これが情報格差なのだ。
新しい法律を知って大家は主導権を取り戻そう
賃貸住宅管理業法ができたからには、これまで管理会社が主体的に決めてきたことは、「そうは問屋が卸さない」ことになるかも知れない。
なぜならば、これまでは管理会社の業務を規制する法律もなければ罰則もなかったからだ。これからは法律を守らなければ罰が与えられる。なによりも、これまで管理会社を取り締まる監督官庁は存在しなかったのであるが、これからは国交省が取り締まってくれるのである。
管理会社のせいで損害を被った大家は、泣き寝入りするか、それが嫌なら裁判を起こして勝つしかなかったのだが、これからは賃貸住宅管理業法に照らして、大家がおかしいと思えば裁判を起こす前に国交省に苦情申し立てすることができる。監督官庁でもあり、賃貸住宅管理業法を所管する国交省は、受け付けた苦情について調査をして、必要があれば管理会社を監督指導してくれるのである。
これまで煮え湯を飲まされてきたと感じている大家は、この新しい法律のことをよく勉強し、管理会社との契約をよく検証して、自分が主役に躍り出るつもりで賃貸業に取り組んでほしいものだ。
大家が押さえておくべき新しい法律のツボ
さて、そのように大家にとっては心強い味方となる賃貸住宅管理業法であるが、「どうしても押さえておきたいツボ」を3点紹介することとしたい。
ツボ①:一定数(200戸とされる)以上の管理戸数がある場合、国交省への「賃貸住宅管理業」の登録が義務化された。
効果①:登録するには備えなければならないさまざまな業務基準などがあるため、これまでのように「何らの免許も規制もなかった時代のゆるい管理業務」は許されなくなる。登録してしまうと、必然的に国交省の監督を受けることになるため、常に襟を正して業務をしなければならない。なぜならば、法律に違反した場合罰則規定があり、「業務停止処分」や「登録の取り消し」など、重い処分を受ければ、社会的信用を失うだけではなく、業務そのものが行えなくなる。
ツボ②:賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他国交省令で定める事項について、定期的に委託者(大家)に報告することが義務化された。
効果②:これまでも「家賃の集金状況」や「敷金の精算について」など、管理会社から報告を受けていた事項に加えて、「建物の維持保全状況」「設備等の法定点検の状況」「入居者からのクレームへの対応状況」などが定期的に報告すべき事項とされた。義務化される前は「管理会社主導の報告」であったことが、今後は報告事項に対して大家が厳しい視線を向けることで「大家主導の報告」に変わっていくものと考えられる。
ツボ③:賃貸住宅管理業者は、営業所(または事務所)ごとに最低1人以上の「業務管理者」を置かなければならない。業務管理者は、国交省が定める資格・業務経験を満たす必要があり、大家との契約書に定められた管理業務を管理監督することが求められる。
効果③:管理業務専業の会社や、管理部門を仲介部門から独立させている大手もあるが、大手・中小を問わず、賃貸仲介と管理業務が混然一体となっているような不動産業者は多い。営業店長は店舗の責任者であっても、大家一人一人の物件の管理業務のすべてを把握するのは困難だ。今後は、管理業務については業務管理者が法律に定められた業務を管理監督する責任を負う。今までは経験の浅い営業マンが慣れない管理業務で不手際を生じさせることがしばしばあったかもしれないが、今後はそのような事態が減っていくかもしれない。大家にとって業務管理者は、心強い存在になるだろう。
ここに書かれたこと以外にも大家には積極的に新しい法律を知っていただき、自分の物件の管理業務において、管理会社から主導権を取り戻してほしい。
賃貸住宅管理業について | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局
【この著者のほかの記事をみる】
サブリースで大家業をやる人に朗報
大家が主役になる時代の幕開け
増え続ける所有者不明土地、法律改正で止められるか
この記事を書いた人
プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。